骨粗鬆症治療薬の順番、間違えると効果が落ちる?〜プラリアとフォルテオの話〜
- 2025年7月5日
- 読了時間: 3分

骨粗鬆症の治療薬は年々進歩しており、現在ではさまざまな種類の薬が使用可能です。しかし、**薬の「使う順番」**によって効果が大きく変わることをご存じでしょうか?
今回は、**「フォルテオ(テリパラチド)」と「プラリア(デノスマブ)」**という2つの代表的な骨粗鬆症治療薬を例に、その使い方の順番によって得られる効果がどれほど異なるかをご紹介します。
結論:私は「プラリア→フォルテオ」より「フォルテオ→プラリア」を推奨しています
これは、実際に行われた臨床試験「DATA-switch試験」(Lancet 2015; 386: 1147)の結果に基づいた私見です。
テリパラチド(フォルテオ)とデノスマブ(プラリア)の違い
薬剤名 | 商品名 | 働き | 使用期間 |
テリパラチド | フォルテオ、テリボン | 骨を“作る”薬(骨形成促進) | 最大2年 |
デノスマブ | プラリア | 骨を“壊さない”薬(骨吸収抑制) | 長期使用可 |
どちらも骨粗鬆症治療に有効な薬剤ですが、「先にどちらを使うか」がその後の効果に影響します。
DATA-switch試験とは?
対象:
45歳以上の閉経後女性
骨折リスクが高い方
試験デザイン:
4年間の追跡
以下2群に分けて評価
フォルテオ→プラリア群:1〜2年目にフォルテオ、3〜4年目にプラリア
プラリア→フォルテオ群:1〜2年目にプラリア、3〜4年目にフォルテオ
試験結果の要点
1. 腰椎の骨密度
フォルテオ→プラリア群:4年間で18.3%上昇
プラリア→フォルテオ群:4年間で14.0%上昇(一時的な減少あり)
▶ 有意差は小さいですが、**安定して上昇するのは「フォルテオ→プラリア」**でした。
2. 大腿骨の骨密度(より重要)
フォルテオ→プラリア群:8.3%上昇
プラリア→フォルテオ群:4.9%上昇(3年目に一度減少)
▶ こちらは明確に差がつきました。「フォルテオ→プラリア」の方が効果的です。
なぜ順番で差が出るのか?
骨の新陳代謝(骨代謝)は「作る」と「壊す」のバランスで成り立っています。
フォルテオ(骨を作る薬)は、骨がある程度壊されている状態でないとその効果が発揮しづらい
プラリア(骨を壊さない薬)を先に使用すると骨代謝が停滞し、あとからフォルテオを使っても効果が出にくい
特に大腿骨のように皮質骨の割合が多い部位ではその影響が顕著に現れます。
腰椎ではなぜ差が少ない?
腰椎は海綿骨が多い部位で、薬の影響を受けやすいため、順番による影響が比較的小さくなると考えられています。
まとめ
フォルテオとプラリア、どちらも優れた骨粗鬆症治療薬です
ただし、「プラリア→フォルテオ」より「フォルテオ→プラリア」の方が効果的
特に大腿骨の骨密度改善ではその差が明確です
薬の「順番」にも注目しながら、患者さん一人ひとりに合った治療選択が重要ですね。
🏠 逗子・葉山・横須賀・鎌倉・横浜市周辺で在宅医療をご希望の方へ
さくら在宅クリニックでは、在宅での骨粗鬆症治療もご相談いただけます。
📺 YouTubeでも在宅診療の知識を発信中!👉 内田賢一 - YouTube

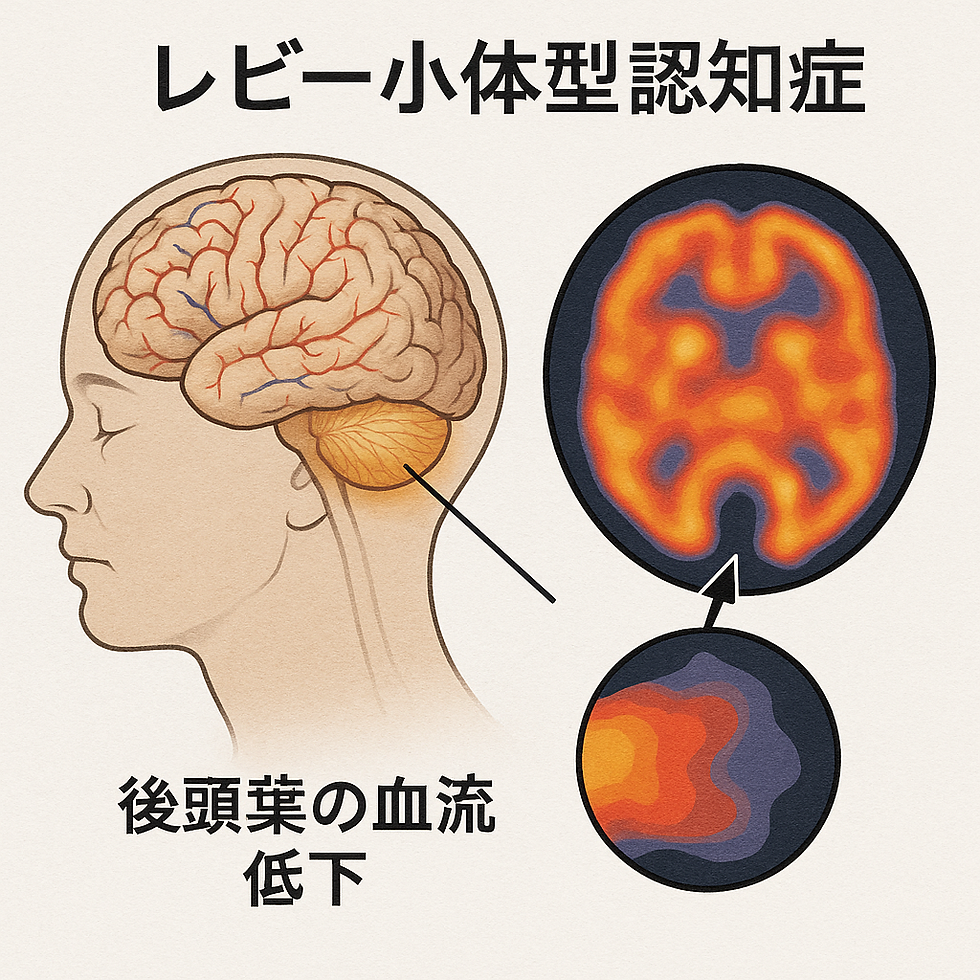


コメント