在宅医療における認知症について37~身体疾患に潜むBPSD悪化要因 ― 感染症・脱水・痛み・感覚障害に注意
- 2025年9月25日
- 読了時間: 2分
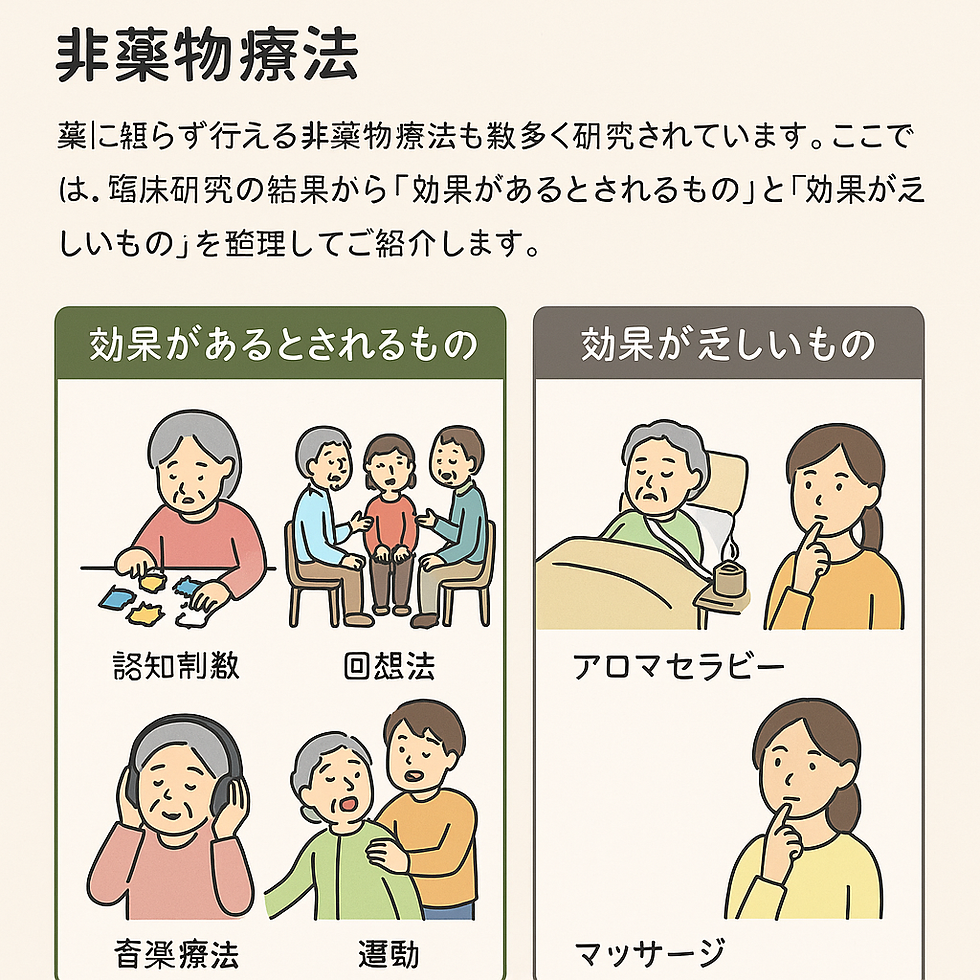
認知症の人にみられる行動・心理症状(BPSD)が悪化したとき、背後に 身体的な原因 が隠れていることがあります。
実際、在宅でBPSDを抱える認知症の方を対象にした調査では、血液検査や尿検査によって 尿路感染症・高血糖・貧血など未診断の病態が34.1%に見つかった と報告されています。
BPSDを悪化させる身体的要因
感染症
高齢者の肺炎は発熱や咳が目立たないことも多く、認知症の方では訴えが乏しいため気づきにくいですが、これがBPSD悪化の原因となることがあります。
脱水・代謝異常
糖尿病の方は高血糖でも低血糖でも精神症状や意識障害につながることがあります。脱水や電解質異常も同様です。
疼痛・かゆみ・便秘
疼痛やかゆみ、便秘といった一見ささいな身体症状も、実は「焦燥感」や「落ち着きのなさ」といったBPSDの原因になり得ます。ある研究では、鎮痛薬で痛みを治療したところ、認知症患者の精神症状(特に焦燥)が大きく改善したと報告されています。特にアセトアミノフェンだけで改善する例も多く、日常生活動作の改善につながることが示されました。
感覚障害
視力低下 は幻視の誘因になります。
聴力低下 はコミュニケーションを妨げ、孤立や混乱につながります。
眼鏡や補聴器の適切な使用も、BPSD予防に大きく役立ちます。
痛みを見逃さないために
認知症の人は、痛みを言葉でうまく表現できない場合があります。そのため、疼痛が焦燥や興奮という形で表れることがあります。
重度の認知症の方には、観察に基づいて痛みを評価する PAINADスケール(Pain Assessment in Advanced Dementia)が有効です。
0点:疼痛なし
1〜3点:軽度の疼痛
4〜6点:中等度の疼痛
7〜10点:重度の疼痛
こうしたツールを活用することで、見逃されがちな痛みを適切に把握できます。
まとめ
BPSD悪化の背後には 感染症・脱水・痛み・視聴覚障害 など身体的要因が潜んでいることがある
尿検査・血液検査などで未診断の病態が見つかることも多い
鎮痛薬や感覚補助(眼鏡・補聴器)によって精神症状が改善するケースもある
「BPSD=認知症そのもの」と決めつけず、まず身体的な原因を除外することが大切
📺 在宅医療・認知症ケア・呼吸器疾患の解説をYouTubeで配信中!▶ 内田賢一 - YouTubeチャンネル
🏷 ハッシュタグ#認知症 #アルツハイマー病 #BPSD #在宅医療 #身体疾患 #さくら在宅クリニック




コメント