【在宅診療での腹部膨満感への対応】〜腹水だけじゃない、イレウスの可能性にも注意を〜
- 賢一 内田
- 2025年6月22日
- 読了時間: 4分

がん患者さんの「お腹の張り」は、消化器がんに限らず婦人科がんや泌尿器がんなど、多くのがん種でみられます。しかし、腹部膨満=腹水と短絡的に考えるのは危険です。
■ 腹部膨満の裏に潜む「イレウス(腸閉塞)」
がん患者さんの腹部膨満感の原因として、**イレウス(腸閉塞)やサブイレウス(不完全閉塞)**がしばしば見逃されます。特徴的な症状は、
腹痛
嘔気・嘔吐
腹部の鼓音(打診)
金属音(聴診)
などです。
在宅医療でも診察とポータブルエコーによりある程度診断が可能です。できればポータブルレントゲンも活用できると、より確定診断に近づきます。
【治療の5つの柱】
ステロイド投与
消化管分泌抑制薬(サンドスタチン等)
中枢性制吐剤(セレネース・アタラックスPなど)
経口摂取の調整(無理に食べさせない)
輸液量のコントロールと腹痛へのオピオイド
【ポイント①:経口摂取は「希望」か「安全」か】
薬で嘔気が軽減すると「何か食べたい」と希望されることがありますが、食べると再び症状が悪化するリスクがあるため、選択肢として以下を提示しましょう:
「つらくなるかもしれないけど、食べてみる」
「あえて控えて、安定を保つ」
腹部膨満や腹痛は内臓痛としてオピオイドで対応します。蠕動抑制を避けたい場合はフェンタニル、症状緩和を優先して蠕動を抑えたい場合はモルヒネが有効です。
【ポイント②:NGチューブの活用】
NGチューブ(鼻胃管)の一時的使用は、胃や腸の拡張を防ぐために有用です。ただし、「24時間入れっぱなし」ではなく、患者の希望に合わせて夜間のみ・症状時のみ間欠的に使用するなど、柔軟に対応しましょう。
【ポイント③:なぜ輸液を「絞る」のか】
予後が限られたがん患者さんでは、過剰輸液により腸液分泌が増え、腸管拡張→症状悪化の悪循環に陥ります。
1日あたり500ml程度の「不感蒸泄量」を目安に輸液調整
サンドスタチン(オクトレオチド)併用で腸管分泌を抑え、腸浮腫が改善→再開通することも
浮腫・胸水・腹水があるかを毎日フィジカルで確認し、BUN/Crで脱水バランスもチェックしましょう。
【ポイント④:口腔ケアの重要性】
口腔内の不衛生は嘔気を助長
強い口渇→水を飲んで悪化、という悪循環も
イレウス時には肺炎のリスクも上がるため、口腔ケアを積極的に。難しい場合は口腔外科や緩和ケアチームへの相談を。
【ポイント⑤:ステロイド・サンドスタチンの使い方】
ステロイド(デカドロン)
再開通率は低いが、症状緩和目的で使用
デカドロン4〜8mg/日を朝1回投与
3〜7日で効果評価、なければ中止を検討
サンドスタチン(オクトレオチド)
皮下注が基本。1日300μgをシリンジポンプで持続投与
早期導入が奏功しやすく、結果的にコストも下がる可能性
混注も可能だがQOLへの配慮を最優先に
【プリンペラン(メトクロプラミド)の注意点】
完全閉塞時には禁忌!腸破裂リスクも。ただし不完全閉塞で排便が促される場合には2〜6Aの低用量持続投与も選択肢。副作用(アカシジア・パーキソニズム)にも注意。
【制吐剤の併用】
症状緩和のタイムラグを補うために、以下の中枢性制吐薬を補助的に使用します:
クロールトリメトン(抗ヒスタミン)
セレネース(抗ドパミン)
眠気と効果のバランスを見て調整。
【在宅処方例】
textコピーする編集する
●サンドスタチン 300μg/日(50μg×6A)を持続皮下注(0.2〜0.25cc/h) ●デカドロン8mg+生食100mlを朝1回点滴 ●中枢性制吐薬:アタラックスP 50mg 1A混注
在宅でも、イレウス診療はここまでできる。
患者さんのQOLを最大限に保ちながら、安全に緩和医療を届けるには、的確な診断力と、柔軟な薬剤調整、そして丁寧な説明が不可欠です。
ぜひYouTubeでも、在宅診療の実践を学んでみてください。

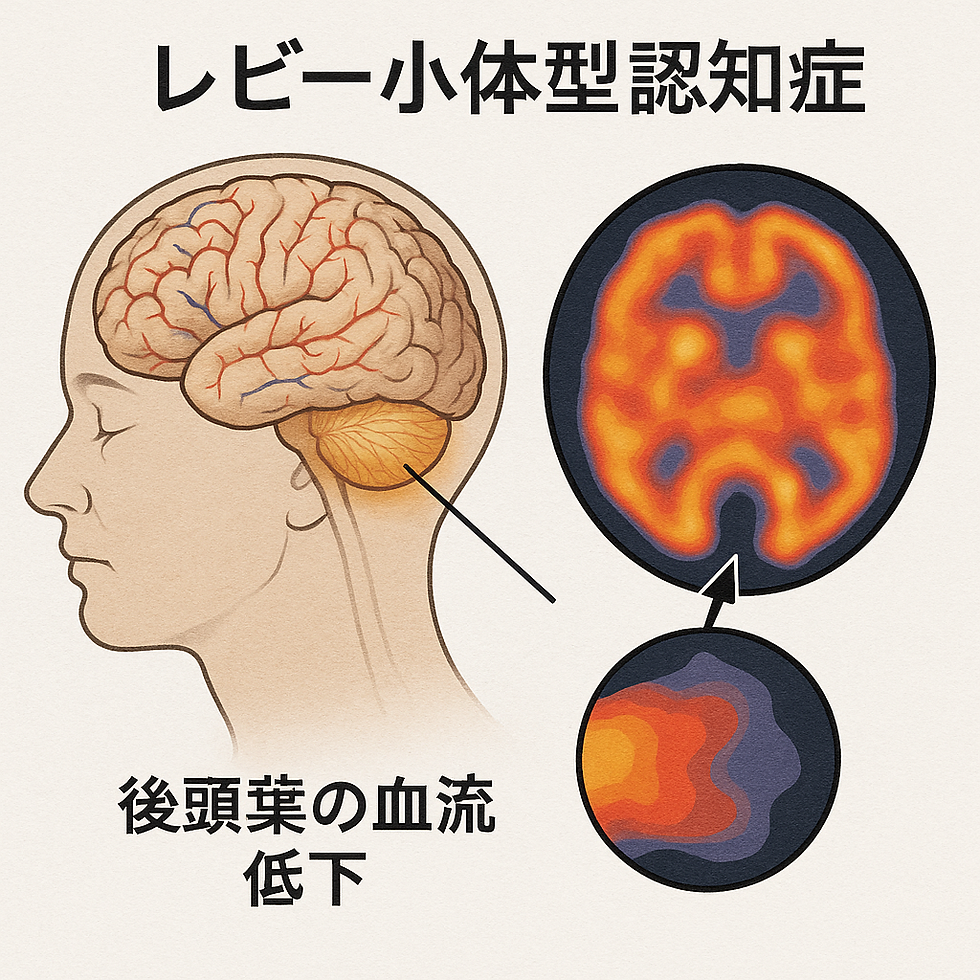


コメント