パーキンソン病と認知症の関係 〜若手時代の気づきと臨床経験から〜
- 賢一 内田
- 2025年4月20日
- 読了時間: 2分

医師として最初の研修年、神経内科の先生が脳外科をローテーションされていた時期がありました。その際に多くのことを教えていただいたのですが、とりわけ印象に残っているやりとりがあります。
「パーキンソン病って認知機能障害あると思う?」「……あると思います」「いいね、その通り」
あまり褒められる経験がなかった研修医時代、そんな一言が強く記憶に残っています。
■ パーキンソン症候群が多いと感じた臨床経験
その後、脳神経外科医として多くの認知症の患者さんを診る中で、「なぜこんなにパーキンソンに似た症状(パーキンソニズム)の方が多いのか?」と感じるようになりました。
パーキンソニズムとは、「錐体外路症状」と呼ばれる運動障害の一種で、脳幹・小脳・大脳基底核などの異常で起こります。
■ 錐体外路症状と変性疾患
この錐体外路症状を引き起こす疾患の多くは「変性疾患」に分類されます。代表例が パーキンソン病。これは中脳の「黒質」という非常に小さな領域に、異常なタンパク質が蓄積し、ドーパミンを分泌する神経細胞が障害を受ける病気です。
■ パーキンソン類縁疾患とは?
パーキンソン病とよく似た症状を呈する他の疾患を総称して「パーキンソン類縁疾患」と呼びます。これには以下のような疾患が含まれます。
多系統萎縮症(MSA) ※かつて「線条体黒質変性症」や「オリーブ橋小脳変性症」とも呼ばれていました
進行性核上性麻痺(PSP)
脊髄小脳変性症(SCD)
いずれも「指定難病」とされる希少疾患で、パーキンソン病とは異なる病理を持ちつつ、運動障害や認知障害をきたす点で類似しています。
■ パーキンソン病と薬物の影響
パーキンソン病の治療は、ドーパミン系の機能を補うことが基本です。そのため、ドーパミンを補充・活性化する薬(L-ドーパやドパミンアゴニストなど)が使われます。
しかし、ドーパミンは過剰に作用すると幻覚や妄想を引き起こすこともあり、認知症がある高齢者では注意が必要です。
一方、認知症の「興奮」や「妄想」などを抑えるために使われる抗精神病薬は、ドーパミンの働きを抑制してしまうため、パーキンソン症状を悪化させる可能性もあります。
🔍 もっと知りたい方へ
📘 在宅医療のリアルを知るなら🔗 さくら在宅クリニック公式サイト(逗子・葉山・鎌倉・横須賀)
🎥 YouTubeでも解説しています🔗 内田賢一の在宅医療チャンネル

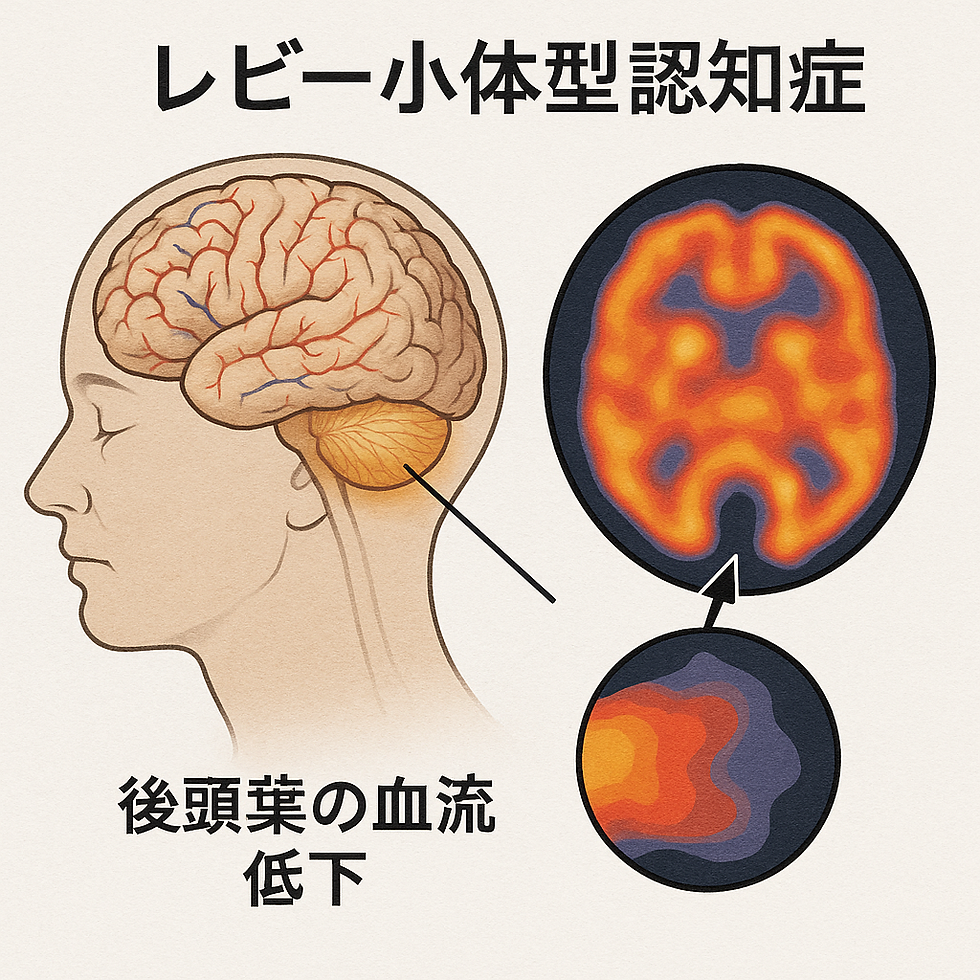


コメント