高齢者の転倒を防ぐために 〜繰り返す転倒の背景と薬の見直し〜
- 賢一 内田
- 2025年7月15日
- 読了時間: 3分

高齢者にとって転倒は、大腿骨骨折や頭部外傷など重大な後遺症を引き起こすリスクがあるため、日頃からの予防が重要です。本記事では、転倒を繰り返す2症例の検討を通じて、転倒リスクの因子と薬物の見直しの重要性について考察します。
転倒のリスク因子
転倒の要因は多岐にわたり、以下の3つのカテゴリに分けられます。
<内因性リスク>
歩行・バランス障害
末梢神経障害、前庭神経障害
筋力低下
視力障害
内科疾患(高血圧、糖尿病など)
高齢そのもの
ADL低下
起立性低血圧
認知症
<外因性リスク>
家屋内の危険物(段差、絨毯、コードなど)
不適切な履物
身体的拘束・抑制
<誘発因子>
滑り
脱力
めまい
転倒リスクを高める薬剤
転倒を引き起こしやすい薬剤には以下のようなものが挙げられます:
ベンゾジアゼピン系薬(睡眠薬、抗不安薬)
抗精神病薬、抗うつ薬、抗コリン薬
抗パーキンソン薬、降圧薬
利尿薬、抗不整脈薬、α遮断薬
オピオイド系鎮痛薬
抗けいれん薬
これらの薬剤は、眠気、ふらつき、起立性低血圧、注意力低下などを引き起こし、転倒リスクを高めることが知られています。
ポリファーマシーと転倒リスクの関係
複数の薬剤を併用する「ポリファーマシー」状態は、高齢者の転倒や有害事象の増加と強く関連しています。
6剤以上の処方で薬物有害事象のリスクが有意に増加
5剤以上で転倒の発生頻度が明らかに上昇
このため、薬剤の総数は5剤以下に抑えることが望ましいとされています。
症例紹介①
90代女性
既往:高血圧症、脳梗塞後遺症、めまい症、慢性心不全、不眠症
通院困難となり、訪問診療を希望
転倒を繰り返していた
介入前の処方:
ベンゾジアゼピン系薬(セロクエル、メリスロン、バキシル)
抗うつ薬、抗不安薬、降圧薬など含め10剤以上
介入後の調整:
睡眠薬・抗不安薬を減薬/中止
必要最低限の降圧薬と鉄剤、便秘薬に集約
総投与薬剤数を大幅に減少(副作用リスク低減)
症例紹介②
80代女性
転倒に加え、慢性的なふらつき、夜間の排尿による動作増加もあった
処方見直し:
抗ヒスタミン薬・鎮静系薬剤を中止
睡眠薬(メイラックス)を中止し、日中の活動性向上を促す
薬剤数を減らしつつ、便通管理や鉄欠乏性貧血の治療を優先
転倒予防のまとめ
薬はなるべく5剤以内に抑える
ベンゾジアゼピン系薬は極力処方を控える
鉄欠乏や貧血の治療も転倒予防に有用
まとめ
高齢者の転倒リスクは、加齢や疾患による身体的要因だけでなく、「薬の使い方」によって大きく左右されます。とくにベンゾジアゼピン系薬の使用には慎重を要し、漫然とした多剤併用(ポリファーマシー)を避けることが重要です。薬の見直しは、医師・薬剤師・看護師が連携して行うべき介入の一つであり、転倒予防の第一歩です。在宅医療・認知症ケア・呼吸器疾患についてYouTubeでもわかりやすく解説中!
▶ 内田賢一 - YouTubeチャンネルhttps://www.youtube.com/@sakurazaitaku

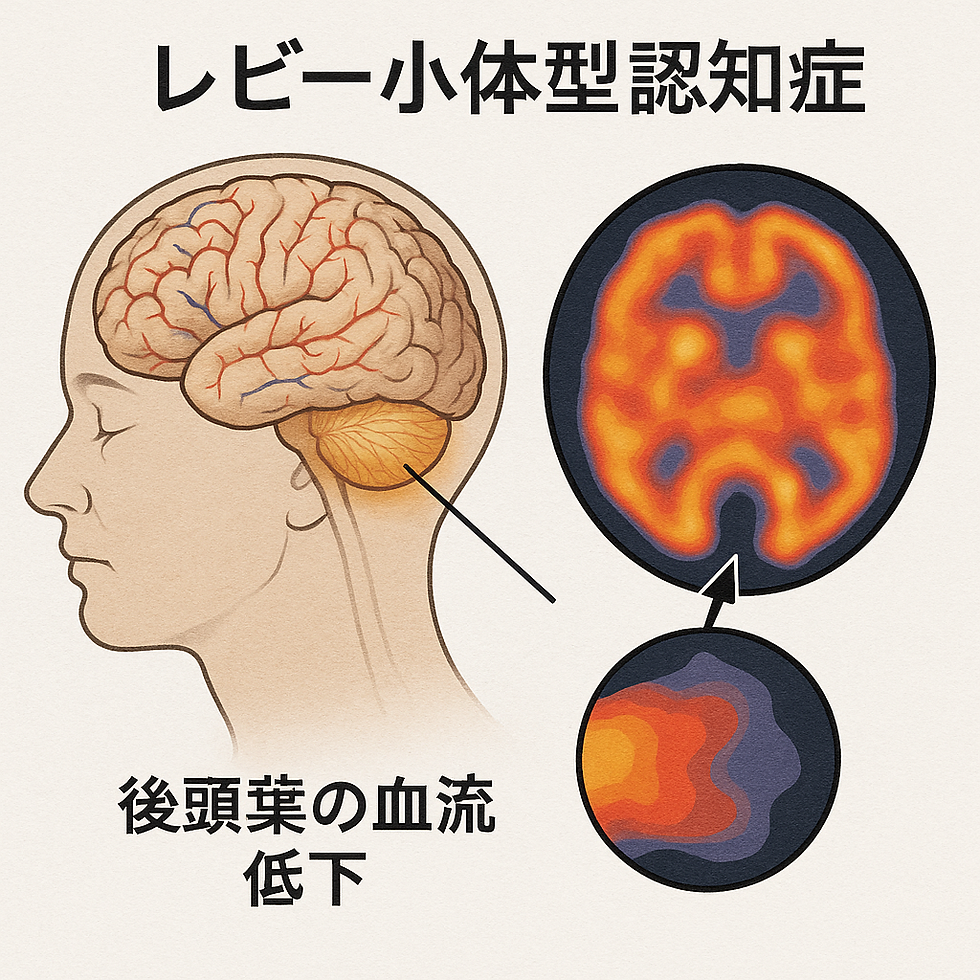


コメント