「不穏」に対するアプローチ②―非薬物的アプローチの基本と限界を知る―
- 賢一 内田
- 2025年7月27日
- 読了時間: 2分

◆ 非薬物的アプローチ vs 薬物的アプローチ
不穏な状態を呈する背景には、「せん妄」や「認知症に伴う行動・心理症状(BPSD)」が代表的です。対応としては大きく分けて、
非薬物的アプローチ
薬物的アプローチ
の2つがありますが、どちらが重要というよりは、両方に適切な役割があります。
◆ まずは非薬物的アプローチから
非薬物的アプローチは、特にせん妄やBPSDの予防・早期介入として非常に重要です。以下に代表的な工夫をまとめます。
■ 物理的環境の整備
昼夜のリズムづくり(自然光、照明の調整)
温度・音・明るさなどの快適な環境設定
眼鏡や補聴器の使用(感覚入力の補助)
カレンダー・時計・家族写真の配置
物品や場所の明確な表示
■ 人的環境の整備
優しい声かけ、落ち着いたコミュニケーション
過干渉を避けたケア
日中の適度な活動(リハビリやアクティビティ)
スタッフ間の連携と情報共有
◆ 非薬物的アプローチの“限界”
とはいえ、非薬物的介入だけで劇的に改善する例は、そう多くはありません。すでに現場ではせん妄予防の取り組みが徹底されており、「できる限りの環境調整はしている」ケースも多いのが実情です。
それでも「どうしても落ち着かない」「周囲に危険が及ぶ」などの状況になれば、薬物治療も選択肢として検討すべきタイミングです。
◆ 介入の判断ポイント
非薬物的な対応で様子をみられるかどうかを判断するために、以下の視点が重要です:
転倒・転落など身体的リスクが高くないか
他者や自分への暴力・暴言が出ていないか
必要な医療・看護行為を安全に受けられているか
これらに問題がある場合、薬物的アプローチをためらわずに導入すべきです。
◆ 薬物治療=「悪」ではない
薬物療法や身体拘束は、時に「できるだけ避けるべきもの」として語られがちですが、適切な場面で正しく使うことは、患者さんを守るための重要な医療行為です。
大切なのは、「非薬物的な工夫を尽くしても限界がある場面がある」ことを認識した上で、その時には過不足なく、柔軟に薬物的アプローチを併用するという視点です。
◆ まとめ
不穏への対応は、非薬物的アプローチが基本
ただし環境調整だけでは限界がある場面も多い
危険の有無や周囲への影響を見極めて薬物療法も適切に導入
すべては患者さんの安全と尊厳を守ることが目的
次回は、「薬物的アプローチ」をテーマに、不穏への具体的な治療戦略について考えてみたいと思います。
▶ さくら在宅クリニック|逗子市・在宅医療

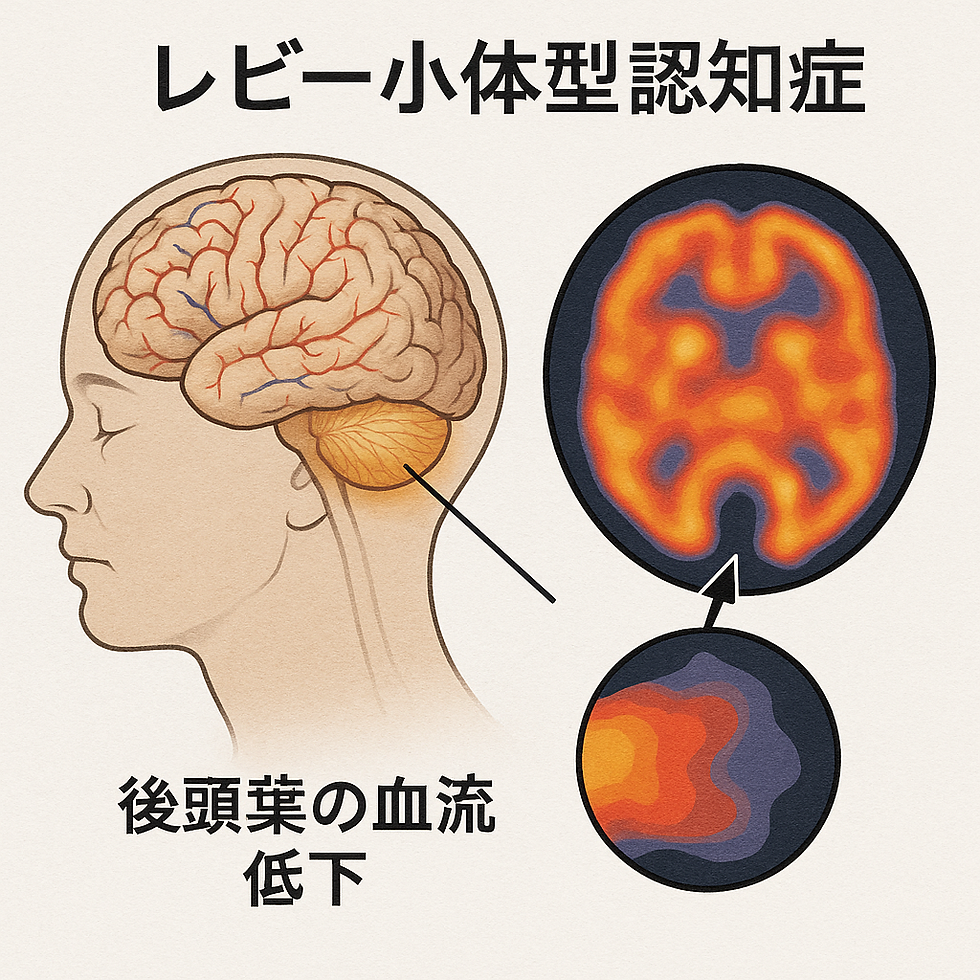


コメント