「不穏」に対するアプローチ③―薬物的アプローチとその実際―
- 2025年7月28日
- 読了時間: 3分

「不穏な状態が続いてどうにもならない」「環境調整や声かけだけでは限界がある」そんなとき、薬物的アプローチは現場にとって重要な選択肢のひとつです。
今回は、主にせん妄や**BPSD(認知症に伴う行動・心理症状)**に対する薬物治療について、その基本的な考え方や注意点をお伝えします。
◆ 薬物療法は“時間を稼ぐ手段”
薬物的アプローチの基本は、根本治療ではなく一時的な症状緩和の手段であることです。
背景にある身体疾患の治療が整うまでのつなぎ
療養環境を調整するまでの時間稼ぎ
精神疾患(うつ病、統合失調症など)が疑われる場合の精神科受診までの橋渡し
薬によって「不穏」という状況を一時的に落ち着かせ、治療や生活支援をスムーズに進めるための準備時間を作るというイメージが近いでしょう。
◆ 高齢者における薬物使用の原則
不穏の多くは高齢者にみられるため、次のポイントは特に重要です。
必要最小限の用量・期間で使う
効果と副作用を丁寧に見極める
漫然と継続せず、見直す機会を持つ
薬物治療は「最小限かつ最短期間で」の原則が基本です。
◆ 保険適応の壁と現場の工夫
実は、せん妄やBPSDに対して明確に保険適応がある薬はごくわずかです。
唯一、**チアプリド(グラマリール®)がせん妄に対する適応を有していますが、現場では、症状に応じて以下のような抗精神病薬の「適応外使用」**が一般的となっています:
クエチアピン(セロクエル®)
リスペリドン(リスパダール®)
ハロペリドール(セレネース®、リントン®)
ペロスピロン(ルーラン®)
これらの薬剤は、2011年に厚労省より「器質性疾患に伴うせん妄・精神運動興奮状態・易怒性」への使用を審査上容認するとの通知が出されており、臨床使用はしやすくなりました。
しかしながら、保険適応が通っているわけではないため、使用に際しては
家族への丁寧な説明
文書によるインフォームドコンセント
副作用や薬の目的の明確化
が欠かせません。
◆ 倫理的な配慮も忘れずに
せん妄や認知症の患者さんでは、理解力や判断力が大きく低下していることがあります。
そうした中で薬物を使うことの是非や、本人の意思決定が困難な状況下での治療介入にあたっては、倫理的な側面にも十分配慮することが必要です。この点もご家族とよく話し合いながら進めていくことが大切です。
◆「向精神薬」と「抗精神病薬」の違い
※ちょっとした豆知識混同されがちですが、以下のような違いがあります。
向精神薬:精神機能に作用する薬全般(抗不安薬、抗うつ薬、睡眠薬なども含む)
抗精神病薬:向精神薬の一種で、主に幻覚や妄想を抑える薬(統合失調症の治療などに使用)
◆ まとめ
薬物療法は不穏状態を一時的に安定させる手段
使い方には慎重な判断と家族への説明が必須
非薬物的アプローチとの併用が原則
保険適応外であっても、臨床上の必要性をもって正しく使うことが大切
不穏に対する薬物治療は、患者さんの生活の質と安全を守るための“手段の一つ”です。薬を「避けるもの」と捉えるのではなく、「適切に使えば助けになるもの」として、バランスの取れた判断が求められます。
▶ さくら在宅クリニック|逗子市・在宅医療

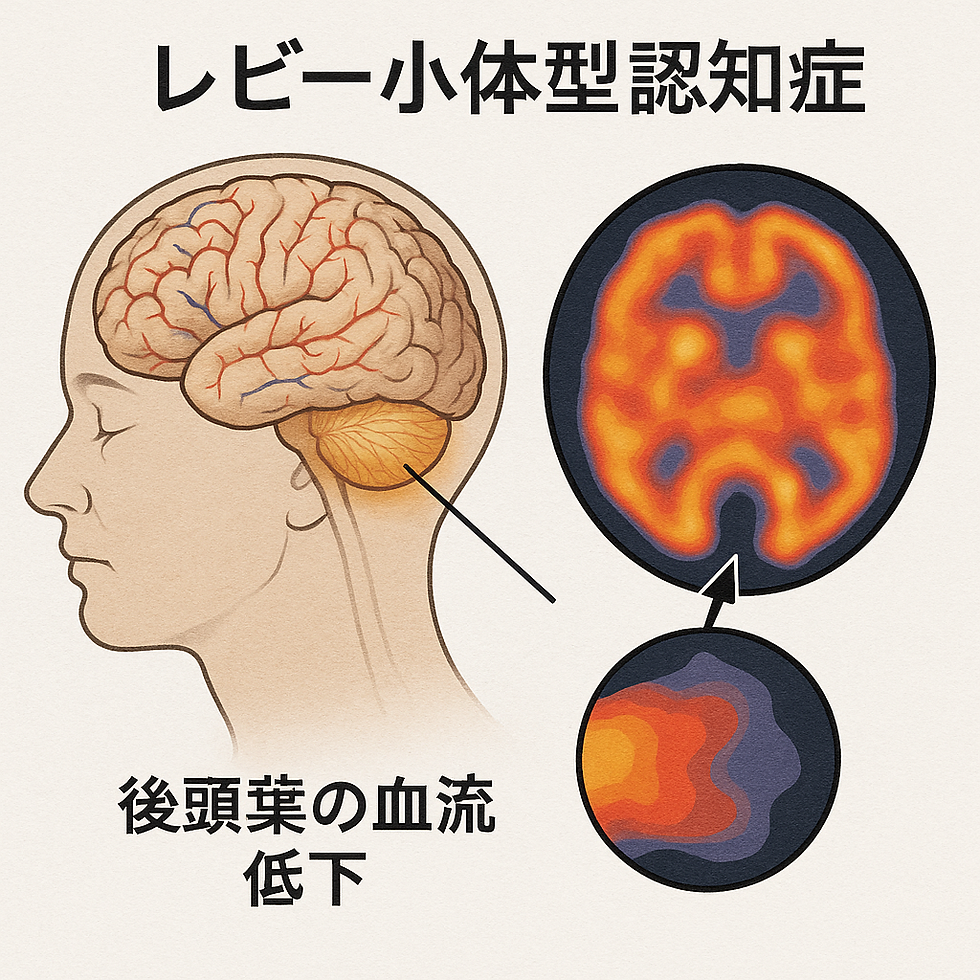


コメント